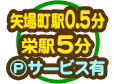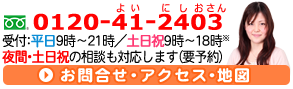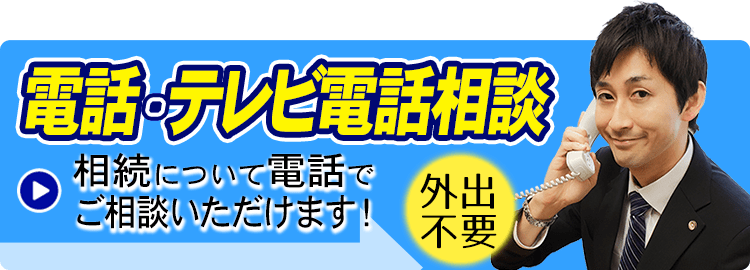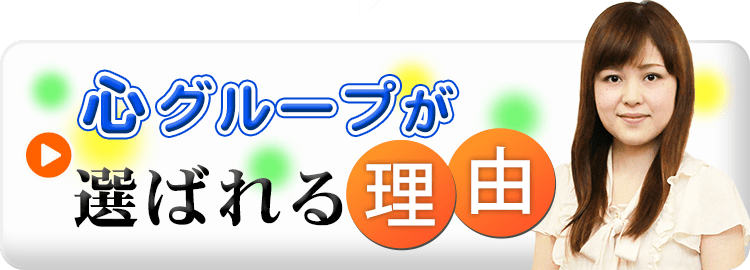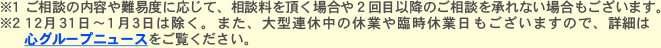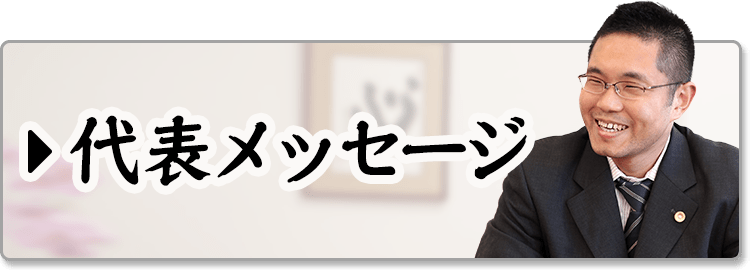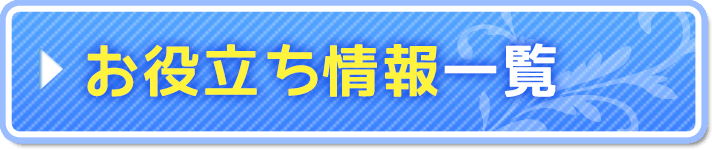相続登記を自分でする際に注意すること
1 遺言書があるかどうかによって書類が異なる
相続登記をする場合、遺言書があるかどうかで必要な書類が異なります。
基本的には、遺言書がない場合には、相続人を確定するための戸籍を準備する必要があります。
相続人を確定するためには、基本的に、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の現在戸籍が必要になります。
これに加えて、該当の不動産を誰がどのように取得するのかを記載した遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書が、基本的には必要になります。
他方、遺言書がある場合には、遺言書に加えて、被相続人が死亡した旨の記載がある戸籍、登記の申請者が相続した旨の分かる戸籍等の書類が必要になります。
このように、相続登記をする場合には、遺言書があるかどうか等で必要な書類が異なりますので、注意しましょう。
2 住所がつながっていない場合への対応
相続登記の際、不動産の名義人が、被相続人と一致していることを確認する必要があります。
被相続人の戸籍の除附票等の記載が、不動産の名義人の住所と一致していればよいのですが、住所変更の登記がなされておらず、古いままの住所のままになっており、戸籍の除附票などで、その住所であったことが確認できない場合があり、このような状態を「住所がつながっていない」と表現することがあります。
このような場合には、本来、相続登記には権利証は不要とされているものの、この問題の解決のために、権利証を提出するという対応方法があります。
権利証が見つからない場合などには、その他の方法で対応ができないかを検討しなければなりません。
どのような書類が必要とされるのかは、法務局によって運用が異なる可能性がありますので、このような場合には、相談をしながら進めるのがよいでしょう。
追加の書類も必要になる場合がありますので、住所がつながっていないときには特に注意をして進めましょう。