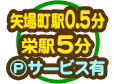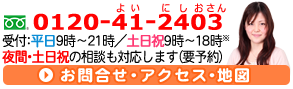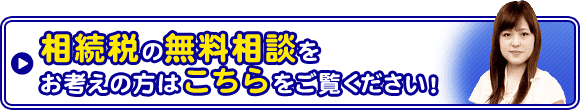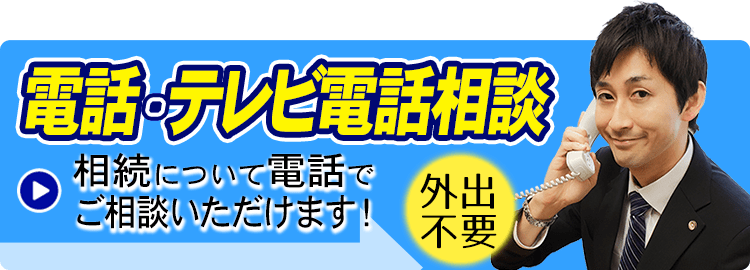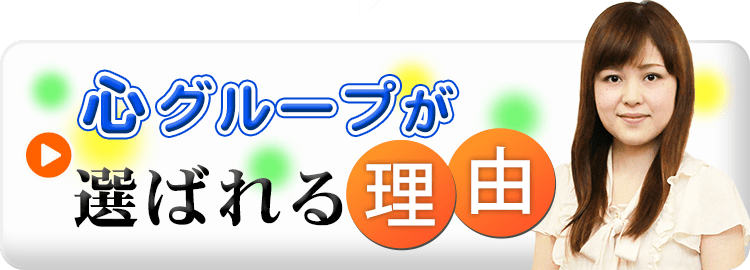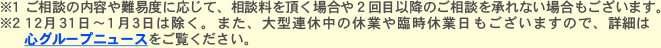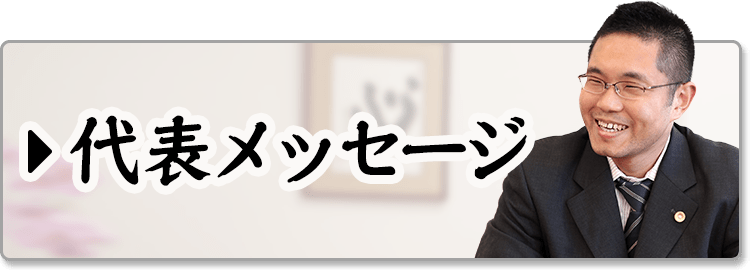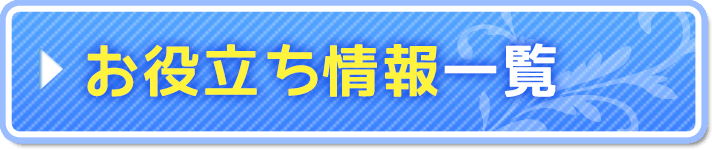二次相続における相続税
1 二次相続における注意点
二次相続とは、両親の相続のうち2番目に発生した相続のことをいいます。
たとえば、両親のうち先に父親が亡くなった場合、父親の相続のことを一次相続、次に亡くなった母親の相続のことを二次相続といいます。
二次相続の際の相続税には注意が必要です。
2 二次相続にでは配偶者の税額軽減が使えない
というのも、一次相続のときには、配偶者の税額軽減が使える一方で、二次相続のときには、これが使えないからです。
配偶者の税額軽減は、配偶者の取得する財産が、1憶6000万円、または、配偶者の法定相続分相当額までは、配偶者に相続税がかからないという制度です。
この制度を利用すれば、非常に高額の相続税の軽減を図ることができますし、配偶者がすべての財産を取得することになった場合、相続税がかからないという結果になるケースも多くあります。
しかし、二次相続のときには、配偶者がいませんから、配偶者の税額軽減を利用することができません。
そのため、この制度を利用して、相続税を大幅に軽減するということができなくなりますので、場合によっては、多額の相続税を支払うことになるケースがあります。
3 相続人の数の変化
相続税には基礎控除額があり、これを超えた部分について相続税がかかります。
基礎控除額は、原則として、3000万円に、600万円に相続人の数を乗じた額を加えて計算します。
二次相続においては、一次相続よりも相続人の数が少なくなっている可能性が高いため、その場合には基礎控除額が少なくなってしまい、相続税が高くなってしまうおそれがあります。
たとえば、一次相続では、妻と2人の子どもが相続人であった場合、基礎控除額は4800万円となりますが、二次相続では、子ども2人だけが相続人となり、基礎控除額は4200万円に下がってしまいます。
実際には相続税の計算方法は複雑なものがあり、基礎控除額が下がったとしても、一概に、一次相続よりも二次相続の方が、相続税額が高くなるとも言い切れない面がありますし、二次相続で、一次相続にはなかった代襲相続が発生した結果、相続人の数が増えるということもあります。
ただ、一般的には、基礎控除額が減少した結果、相続税額が高くなってしまう可能性があることに注意しなければなりません。
4 小規模宅地等の適用
被相続人の居住用に使用されていた土地は、小規模宅地等の特例を利用することで、価額を下げることが可能なケースがあります。
この特例を利用することができれば、330㎡までの土地について8割まで価額を下げることができますので、非常に大きな効果があるといえます。
この特例を利用するための要件には、上記の居住用に利用されていた土地であることに加えて、相続人の誰が相続したかというものもあります。
配偶者が取得するのであれば、無条件で、この特例を適用することができます。
そのため、一次相続のときには、配偶者が自宅を相続することで、居住用財産として小規模宅地等の特例を利用して、相続財産額を抑えることができる可能性が高いです。
ただ、二次相続のときには、自宅を相続する者が小規模宅地等の特例の適用の要件を満たしているかどうかは確実ではありません。
土地を相続した相続人が同居の親族であって、その他の要件を満たしている場合や、いわゆる「家なき子特例」の要件を満たす場合には、特例を適用して、相続税額を抑えることができます。
そのほか、居住用宅地以外の小規模宅地等の特例を適用できないかなどの点を検討する必要もあります。
5 二次相続も踏まえて遺産分割内容を検討することが大切
上記のように、二次相続においては相続税についての十分な考慮をしなければなりません。
これは、一次相続のときから、二次相続のことも踏まえたうえでの遺産分割内容を考えなければならないということを意味します。
すなわち、一次相続において、配偶者が多くの財産を取得することにした場合には、一次相続では相続税額を抑えることができるものの、二次相続では、多くの相続税を支払わなければならないおそれが生じます。
そのため、一次相続において一定の遺産分割内容にした場合には、二次相続においてどの程度の相続税の発生が見込まれるのかをシミュレーションする必要があります。
そこでは、上記のような、基礎控除額の変化、小規模宅地等の特例の適否なども考慮することになりますし、もともと配偶者にどの程度の財産があったということも考慮する必要があります。
そのうえで、一次相続と二次相続のそれぞれでどの程度の相続税の発生が見込まれるのかを計算して、基本的には、発生する相続税の合計がもっとも抑えることができる遺産分割内容を検討することになります。
上記以外の考慮として、一次相続の発生後、二次相続発生までに、相続税対策をする可能性の有無や内容を考慮したり、配偶者の相続財産の増減の可能性を考慮したりすることもあります。
そのような考慮をしたうえで、もっとも適切な一次相続における遺産分割内容を決めていくことになります。